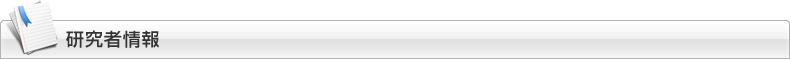せん らあじ・らき (セン ラージ・ラキ) 准教授 Raj Lakhi SEN

所属組織・役職等
国際日本研究教育センター
教育分野
【学士課程】
人間社会学域 国際学類
【大学院前期課程】
人間社会環境研究科 国際学専攻
所属研究室等
国際日本研究教育センター FAX:
学歴
【出身大学院】
筑波大学 博士課程 人文社会科学研究科一貫博士課程 文芸・言語専攻 修了
筑波大学 修士課程 人文社会科学研究科一貫博士課程 文芸・言語専攻 修了
デリー大学 修士課程 修了
【取得学位】
博士号(日本文学)
職歴
金沢大学 准教授(2023-)
同志社大学 嘱託研究員(2021-)
東京外国語大学 助教(専任)(2017-2021)
筑波大学 非常勤講師(2024-)
トリノ大学、イタリア 客員教員(2023-2023)
青山学院大学 非常勤講師 (2017-2024)
白百合女子大学 非常勤講師(2012-2021)
早稲田大学 非常勤講師(2019-2020)
筑波大学 博士特別研究員(2016-2017)
生年月
所属学会
日本近代文学会 運営会員(2019-2021)
日本比較文学会 (国際活動委員会 委員 2025年4月〜)
全国大学国語国文学会 全国大会コーディネーター(2016-2017)
日本社会文学会
アジア研究協会(AAS)
ヨーロッパ日本研究協会(EAJS)
日本研究協会(米国)
東アジア翻訳研究学会
学内委員会委員等
受賞学術賞
○国費留学生 (2008年-2015年)(2008/04/01)
○優秀論文賞(博士)(2016)
○JSPS外国人特別研究員(日本学術振興会)2017(2017)
専門分野
近現代日本文学、文学一般、学際文学、比較文学、日本文化, ジェンダー論
専門分野キーワード
研究課題
著書
- 「日本文学研究のための英語――世界との対話のための英語による日本文学研究」『青山学院大学文学部日本文学科ーー文化交流入門』 武蔵野書院 2023 共著 小松靖彦編
- 「国木田独歩の養子反対論と「不自然」な家族」『異文化理解とパフォーマンス: Border Crossers』 春風社 2017 共著 セン ラージ・ラキ
- 「タイとインドの男色文化、その多様性を巡ってーインドの男色文化を巡って」『男色を描くー西鶴のBLコミカライズとアジアの<性>』 勉誠出版 2017 共著 セン ラージ・ラキ
- 『近現代日本語文学とメディアにおける家族法・制度を考える』 「報告書」中国文化大学、台湾 2019 共著 セン ラージ・ラキ、その他
- 博士論文「明治文学作品を養子法・制度から読み直す」 2016 単著 セン ラージ・ラキ
- 「石上露子の「代替的」な希望——軍国主義の中の「養子」と「天職」」『文学、社会、歴史の中の女性たち〈Ⅱ〉ーー学際的視点から 』 丸善出版 2013 共著 セン ラージ・ラキ
論文
- パンデミックの言説ーインドのパンデミック「ポップテクスト」における「スーパーヒーロー」の出現と多様性をめぐって」 Αυριον, 21号 171-193頁頁 2022 原著論文
- Re-thinking the Acts of Translation during the Time of Insurgency in Mori Ogai and Lu Xun ‘s Literary works: Trans-creating “The Tower of Silence,” セン ラージ・ラキ 『⽇本⽂化の対話と翻訳』タシケト国⽴東洋学⼤学、ウズベキスタン 2018 査読有
- 「食文化の翻訳/翻案―村上春樹が描いたパスタ/スパゲティーを中心に」 『翻訳・翻案と⽇本⽂化―テクストの世界展開をめぐって―』 2016 査読有
- 「ゆく雲」「うつせみ」「われから」における「婿/養子」法・制度——「一人娘」たちの「煩悶」 セン ラージ・ラキ 『文学・語学』第213号 2015 査読有
- 「明治期における「養子/女」——「こしのみぞれ」に代弁されたアイヌ人女性の「声」」 セン ラージ・ラキ 『社会文学』第42号 2015 査読有
- 「文学と法 与謝野晶子『雲のいろいろ』における「養子」と「反対(あべこべ)」」 セン ラージ・ラキ 『言語・文学研究論集』第14号 2014 査読有
講演・口頭発表等
- Between Alienation/Isolation/Loneliness: Women Writers in Contemporary Japanese Literature(会議名:WCAAS 2025 Mexico)(2025/11/07)
- Post-Pandemic Japan and its Challenges (会議名:Hasanuddin University, Indonesia )(2025/06/02)
- 'Who is translating whom? On omissions of the race narratives from Japanese texts into English'(会議名: 5th East Asian Translation Studies Conference, Queensland University, Australia )(2024/06/28)
- 歴史家ワークショップ「多言語論文執筆シリーズ Vol. 21:多言語のなかの日本語 〜研究・発信の言語としての日本語を考える〜」(会議名:歴史家ワークショップ)(2024/12/07)
- 「癒し」の現代文学――日本文学の翻訳事情を中心に(会議名:金沢大学 国際日本研究センター 国際共修・多文化共修の課題と展望― 学際的視点からの探究)(2025/03/14)
- 「文学が代表する法・制度」(会議名:同志社大学)(2023/09/14)
- Paper 'Piano Geniuses: On the verge of Vernacularization of Music in Boy's Manga' Panel: On the Music notes/Graphics: Decoding The Phenomena of Japanese Manga (会議名:Biennial International Conference of CLAI)(2024/11/12)
- 'Pandemic and the Rise of Superheroes in India'(会議名:東京経済大学)(2022/12/23)
- ’Negotiating “Pop-Texts”: Toward a Dialogic Development of Japanese Culture,’ (会議名:TIEC International Symposium 2018, Jasso, University of Tsukuba)(2019/01/13)
- ラウンドテブール対談『ポストコロニアル批評の最前線』(会議名:国際日本コンソーシアム(日本)、開催:慶熙大学校国際キャンパス、韓国)(2018/08/14)
- ファンタジーを超えて ― BLマンガが描く養子法・制度(会議名:「ナラティヴ・メディア研究会」東北大学)(2018/08/04)
- Civil Code and the Meiji Intelligentsia-Socio-Legal Representation of “Adoption” in Literature(会議名:4th Joint Workshop, Freie Universität Berlin- University of Tsukuba, Continuities and Ruptures of Modernization: Perspectives on Japan’s Modern Transformation, Tsukuba, Japan)(2017/04/04)
- Paper: ‘Rewriting History in Relation to Creating ‘Non-natural’ languages in Li Kotomi’s Works’ Panel: Of Trans/Creating the Languages: Japanese text(s) and their Negotiations with Cultural Industry, (peer-reviewed)(会議名:The 4th East Asian Translation Studies Conference, Paris, France)(2022/06/27)
- 文学と法—与謝野晶子の短編集における「養子」制度を事例として(会議名:日本近代文学会全国大会、於法政大学。)(2013/05/26)
- Paper: Laughter as Collective Mis/interpretation: Ariyoshi Sawako’s Furu Amerika ni Sode wa Nurasaji in Kabuki Format’ Panel: The Pitfalls of Universalism: Japanese Cultural Texts Interpreted and Misinterpreted Under the Western Eye, (peer-reviewed)(会議名:17th Annual Conference on Asian Studies (ACAS) organized by the Department of Asian Studies at Palacký University Olomouc,Czech Republic)(2023/11)
- 「モーパッサンと国木田独歩の「自然主義」——「遺傅」と「不/自然」の「養子」制度を事例に」(会議名:日本比較文学会全国大会、於立命館大学。)(2015/06/14)
- Paper: Koseki/Citizenship and Identity in Hirano Keiichiro Novel’s and its Movie Adaptation, Workshop: Japanese Contemporary Literature and its Intersections with Artistic Expressions, (会議名:University of Turin, Turin, Italy)(2023/03/26)
- Panel: ReDiscovery of 'Adultery' as a Neta: Stumbling between 'Natural and Criminals Laws' in Meiji Literature (会議名:European Association for Japanese Studies, Ghent,online)(2021/08)
- '文学と法:植民地支配下の韓国と日本の法' 対談:金富子(歴史学)、本澤巳代子(法学)、セン・ラージ・ラキ(文学) ‘How Did Wives Without Full Legal Capacity Exercise Separate Property Rights?: Examination of Civil Case Records from Colonial Korea’ Sungyun Lim (会議名:東京外国語大学)(2020/02/01)
- paper: ‘Problematics of Law related to Choushi/Chounan-sonzoku (male-primogeniture) discourses in Japanese Novels and the Literature Text book.’ Panel: Imagining Japanese Literature and Law,(会議名:International Comparative Literature Association 2019, Macau )(2019/07/30)
- paper: ‘Self-reassurance and ‘Enlightenment’: Translating Japanese Texts into Indian Languages’, Special Panel: Translation as Intercultural Dialogue. Modern and Contemporary Japanese Texts in Various Contexts.(会議名:The 3rd East Asian Translation Studies Conference ,Ca’ Foscari University of Venice, Italy )(2019/06/09)
- Paper: ‘Trans-creation of Law in Meiji Era and its Interpretations in Japanese Novels.’ Panel: Looking at Modern Asian History through the Prism of Law (会議名:The Joint East Asian Studies Conference 2019, The University of Edinburgh, UK )(2019/09/06)
- Paper: ‘Undoing the Empire of Aesthetical Surgery and ‘Otherness’: Arguing Puchi-zeitaku (Petit Luxury) and Patriotism in Japanese Fiction and Pop-text.’ Panel: Crafting Aesthetics and Ideologies: Reading ‘Symmetrical’ Faces and Bodies in Japanese Novels to Pop-texts. (会議名:International Conference in Comparative Literature. The University of Edinburgh, UK)(2018/12/14)
- ‘Law and Ethics: Adapting ‘Edo' & Adoption Law in Historical Fiction’(会議名:Fiction’Pula University &University of Tsukuba Forum, Pula, Croatia)(2018/09/17)
- Paper: Adaption of Adoption Law on the Verge of Modern-State Building: Decoding Shakespeare’s Tragedies Adapted by Jōno Saigiku’, Panel: Adaptation as Evidence: Japanese Literary Genres & Their Legal Contexts. ‘(会議名:The Association for Japanese Literary Studies , Berkeley, US.)(2018/09/09)
- Pape: ‘Adapting Meiji Legal Codes: The Re-presentation of Jogakusei (school girls) in Miyake Kaho and Higuchi Ichiyo's Novels in Relation to the Meiji Adoption System’ Panel: The Gender of the Law: Re-theorizing the Discourse on Modernity in Late Meiji Legal Notions of Family, Gender and Citizenship(会議名:European Association for Japanese Studies, Lisbon, Portugal,)(2017/06)
- Paper Title: Traversing the “Literature”: Re-interpreting Boys’ Love from Japanese socio-legal context. Panel Title: Precarious Relationship between Literature and Popular Culture in Japan (会議名:Association for Asian Studies, Annual Conference in Toronto, Canada)(2017/03/16)
- “Adoption” in the context of Jogakusei in Meiji Japan(会議名:5th Joint Workshop, Freie Universität Berlin- University of Tsukuba, Continuities and Ruptures of Modernization: Perspectives on Japan’s Modern Transformation, Berlin, Germany)(2016/11/13)
- 食文化の翻訳/翻案——村上春樹が描いた「パスタ/スパゲティー」を中心に(会議名:Tashkent State Institute of Oriental, Studies, Tashkent, Uzbekistan)(2016/03/16)
- Paper Presented: Boys’ Love Genre-The Adoption System as an Instrument for Clandestine Marriage. Panel Title: Beyond "Popular"- Manga as Radical Representation of Socio-Political Issues (会議名:International Graphic Novel and Comics Conference, British Library, London, UK)(2014/07/19)
- Paper: Role of Translation in Modern Literature: MORI Ogai’s “The Tower of Silence ”(会議名:International Conference on Literature Language and Communication: An Essential Trident, Lucknow, India)(2013/12/06)
- Paper: Debates on Law Making Related to Gender Roles in Meiji Era. "Agency" through Eastern Philosophy(会議名:XXth World Congress of the International Comparative Literature Association (ICLA), Paris, France)(2013/07/19)
- 樋口一葉作品における「養子」(会議名:北京師範大学—筑波大学—中日言語文化の交流と共有、中国)(2012)
- 与謝野晶子の小説における男女関係と明治社会(会議名:高麗大学校・筑波大学教頭研究集会、韓国)(2010)
- 明治社会と男女の〈自立〉―与謝野晶子と石上露子の小説を中心に―(会議名:東アジア文学からジェンダーをみる、於国立台湾政治大学、台湾)(2011)
- 日本とインドの狭間(会議名:白百合女子大学 国語国文学会講演会)(2011)
- インド映画における日本/日本人像:The Japanese Wifeを中心に(会議名:日本比較文学会、東京大会)(2016/10/06)
- 「パンデミック言説ーーインドのパンデミックポップテクストを中心に」(会議名:白百合女子大学)(2022/01/31)
- 『文学と法のワークショップ:近現代日本語文学とメディアにおける家族法・制度を考える』「日本語近代文学史における家族法の解釈と英訳を中心に」(会議名:中國文化大學、台湾)(2019/03/09)
その他(報告書など)
芸術・フィールドワーク
特許
共同研究希望テーマ
科研費
○基盤研究(A)「冷戦期東ユーラシア文化外交と英米文学のジオポリティックス」(2024-2028) 分担者
○基盤研究(B)「文学と法のグラマトロジー:日本語文学と法・制度の境界横断を中心に」(2018-2023) 代表者
○ 基盤研究(B)「日本文化の対話的発展の比較文学的研究―世界のポップ・テクストをめぐって」(2018-2022) 分担者
○基盤研究(B)「日本現代文学・文化の世界展開の比較文学的研究―<ポップ>なテクストを中心に」(2014-2018) 分担者
競争的資金・寄付金等
共同研究・受託研究実績
A-STEP採択課題
学域・学類担当授業科目
○近代日本文学入門(2024)
○ジェンダー論から読み解く日本文学(2024)
○近代日本文学―明治期から戦後まで(概論2 )(2024)
○日本文学と翻訳論(2024)
○現代日本文学―戦後から現代まで (概論 1)(2024)
○近代日本文学―明治期から戦後まで(概論1 )(2024)
○近代日本文学入門(2024)
○現代日本文学―戦後から現代まで (概論 2)(2024)
○大学・社会生活論(2024)
○大学・社会生活論(2024)
○日本文化体験D(2024)
○日本文化体験D(2024)
○異文化理解1(2024)
○日本文化体験D(2024)
○日本文化体験D(2024)
○日本文化体験C(2024)
○日本文化体験C(2024)
○日本文化体験C(2024)
○日本文化体験C(2024)
○アジア研究基礎(2024)
○アジア研究基礎(2024)
○異文化理解1(2024)
○日本文化体験D(2023)
○近代日本文学入門(2023)
大学院担当授業科目
○日本近現代文学特論a(2025)
○日本近現代文学演習a(2025)
○日本近現代文学特論b (2025)
○日本近現代文学演習(2025)
○日本比較文学とジェンダー演習1
(2025)
○日本比較文学と比較ジェンダー演習2(2025)